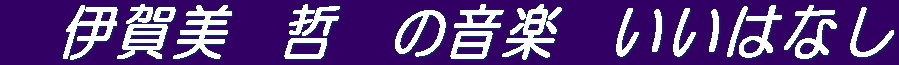
| 第一回 クリスマス・オラトリオ (J.S.バッハ) | 第七回 W.A.モーツァルトと旅 2 |
| 第二回 ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」Op.125 | 第八回 W.A.モーツァルトと旅 3 |
| 第三回 新日本フィルハーモニーのハイドン・プロジェクト | 第九回 ヘンデルとオラトリオ |
| 第四回 歌曲集「冬の旅」(F.シューベルト) | 第十回 モーツァルトと短調の曲 |
| 第五回 オペラの演出について | 第十一回 モーツァルトと長調の曲 |
| 第六回 W.A.モーツァルトと旅 1 | 第十二回 ベートーヴェン:後期弦楽四重奏曲 |
〔第1回〕
〔第2回〕
〔第3回〕
〔第4回〕
〔第5回〕
〔第6回〕
〔第7回〕
〔第8回〕
〔第9回〕
〔第10回〕
〔第11回〕
〔第12回〕
〔第13回〕
〔第14回〕
〔第15回〕
〔第16回〕
〔第17回〕
〔第18回〕
〔第19回〕
〔第20回〕
〔第21回〕
〔第22回〕
〔第23回〕
〔第24回〕
ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」Op.125
例年のように昨年暮れにも日本各地で演奏されたベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱付き」について思うことがあります。
言うまでもなく、ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調(以下「第9」)は、彼の9曲の交響曲のみならず古今東西の交響曲の最高峰と言える。J.ハイドンによって確立した
交響曲 W.A.モーツァルトを経てベートーヴェンへと発展していった。(正確に言うならば、モーツァルトの最後の交響曲は1788年に完成し、ハイドンは最後の104番を1795年に完成しているので、モーツァルトはハイドンに多くの影響を及ぼしたと言える。)所謂ヴィーン古典派の交響曲と呼ばれる。これらは、その後、ロマン派の作曲家即ち、F.シューベルト、F.メンデルスゾーンR.シューマン、J.ブラームス、A.ブルックナーらに受け継がれていった。そもそもヴィーン古典派の交響曲は、伝統的に純粋な器楽曲であった。しかしベートーヴェンの「第9」ご存じのように終楽章に声楽を用いた。その決断にいたる迄にベートーヴェンは、従来の交響曲の範疇から逸脱することから、かなり躊躇したようであった。紆余曲折の末、最終的に声楽入りの交響曲として完成させた。1824年5月7日ヴィーン初演の後も従来の交響曲への拘りを持ち、終楽章を書き直すとも洩らしていたが結局現在演奏されている声楽入りの交響曲として残った。
この第9交響曲も「苦悩を通して歓喜へ」のモットーが根底にある。第1楽章から第3楽章は、終楽章の「歓喜」に至る楽章として準備されている。
私が、この交響曲を初めて聴いたのは15歳の時でした。最初は、終楽章よりも第3楽章の美しさが好きでした。前の二つの楽章を覆っていた暗雲から突如光が射し込んで、天上からコラールが奏でられる第1主題とまさに天国の楽園を思わせるような第2主題をそれぞれ美しく変奏してゆくこの楽章は、この世の最も美しい音楽と思いながら聴いていました。しかし、ロマン・ロランの「第9交響曲」という著作で、ベートーヴェンが「第9」
と同時に作曲していた大作「ミサ・ソレムニス」終結の Dona nobis pacem が、「第9」第3楽章の終わり方に通じ、その解決が「第9」終楽章の「歓喜に寄す」であることを指摘した部分に共感しました。ベートーヴェンは、Dona nobis pacem の導入の前に「内なるそして外なる平和への願い」(Bitte und innern und aussern Frieden)と記入した。ミサ・ソレムニスでは、R.ロランが指摘しているように「外なる平和」は完全燃焼されていない。それが「第9」の終楽章で成就されることとなる。ベートーヴェンは、第3楽章の「内なる平安」で終結させることなく、「外なる平安」をシラーの「歓喜に寄す」でこの崇高な頌歌を歌い上げ、理想とする世界を描ききった。
さて、今回「第9」でお話ししたいことは、冒頭に書いたように、年末の恒例行事のように頻繁すぎるほどに「第9」が演奏されることである。中には、「第9」は12月に演奏すべき曲だと取り違えている人も多い。交響曲の歴史上、極めて高い思想を持った記念碑的なこの作品を年中行事のように取り上げて無下に演奏するのは、この曲の崇高さを思うと残念な思いである。
演奏は、一期一会である。曾て、G.マーラーが弟子のB.ワルターに、自身の第9交響曲について「この曲を一度演奏したら一年間は演奏しないこと」と話したことを、ワルター自身後述している。これと似たような記述が、世阿弥の「風姿花伝」(花伝書)にある。即ち「一つの能を演じたら3ヶ月は同じ能を演じない」旨を述べている。室町時代の著作だが、この書は全篇にわたり西洋音楽にも共通な芸術論を展開していて興味深い。
「第9」に関して私自身の経験でいうと、(プロオケに限っていうと)やはり年末に複数回の演奏に感動した覚えはない。もちろん演奏者も同じ思いで演奏していたと思う。もう30数年前になるが、秋山和慶指揮の東京交響楽団の5月定期だったと思うが、爽やかで新鮮な印象が今でも残っている。もちろんその時一回限りの演奏会であった。
レコード(CD)では、私は、何といっても1951年7月29日のバイロイト音楽祭開幕にW.フルトヴェングラーによるライヴ演奏を越える録音を聴いたことがない。神懸かり的演奏と言える。終楽章の主題が低弦からヴィオラからヴァイオリンへと受け継がれて行く所などまばゆいほどに後光が射しているようである。この演奏会は、戦後中断していたバイロイト音楽祭が再開された時に演奏されたもので、1876年ワーグナーがルードヴィッヒ二世の援助を得て音楽祭を開催した際に、尊敬するベートーヴェンの第9交響曲を演奏したことに因っている。この記録は、まさに一期一会そのものと言える演奏を伝えている。
曲は異なるが、先程のマーラーの第9交響曲をL.バーンスタインがイスラエル・フィルの来日公演で指揮をした時のこと。確か1985年NHKホールであったが、9月8日と12日の二回同じ第9交響曲を演奏した。両日とも一階10列の中央席で聴いたが、8日の演奏は曲が終わっても誰一人すぐには拍手せず、長い祈りのような沈黙があった。バーンスタインは翌日のインタビューで「昨日の演奏会は生涯で最高の演奏であった。聴衆がすばらしかった」といっていた。私もその聴衆の一人としてこの演奏会に臨めたことを嬉しく思えた。そして4日後の同じ演奏者・同じ曲であったが、あれだけの演奏をした彼らは、少なくとも4日前と同じレヴェルかそれを上回る演奏をを求めたと思うが、それは不可能であった。何か必死に前の演奏を追っているようであった。まさに、G.マーラーや世阿弥の言っていることが当てはまるものであった。
また、最近でた映像だが、カラヤン100年メモリアル・コンサートの小澤征爾指揮・ベルリン・フィルの演奏会でのチャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」で、1月23日ベルリンの演奏は、これ以上ないなと思われるようなすばらしいもので団員もそれを感じながら演奏が進んでいったようにみられる。そして、5日後に同じ「悲愴」をヴィーンのムジークフェラインでの演奏は、先のマーラーの第9交響曲と同じようなことが感じとられる。
そのようなことで、年末のプロオケによる「第9」も、興行的にはマイナスと思うが各オケとも一公演ずつにすると、良い演奏も生まれる可能性があるのでは?
伊賀美 哲[いがみ さとる]
国立音楽大学声楽科卒業。波多野靖祐、飯山恵己子諸氏に師事。現在、田口宗明氏に師事。指揮法を故櫻井将喜氏に師事。1982年、第7回ウイーン国際夏季音楽ゼミナールでE.ヴェルバ、H.ツァデック両 教授の指導を受ける。1985年フィンランドのルオコラーティ夏季リート講座で、W.モーア、C.カーリー両教授の指導を受け、その後W・モーア教授にウ イーン、東京で指導を受ける。1986年から毎年、リートリサイタルを開催、シューベルトの歌曲集「冬の旅」、「美しい水車小屋の娘」、「白鳥の歌」、 シューマンの歌曲集「詩人の恋」等を歌う。千葉混声合唱団では、ヘンデル「メサイア」、モーツアルト「レクイエム」、J.S.バッハ「ミサ曲ロ短調」「マタイ受難曲」などを指揮する。現在、千葉混声合唱団、かつらぎフィルハーモニー指揮者。